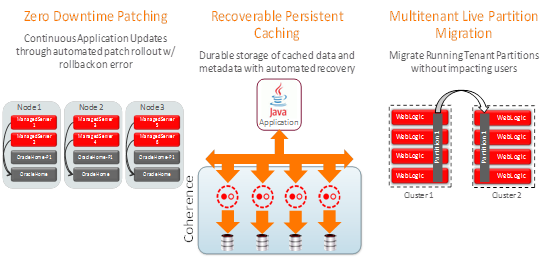原文はこちら。
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/application_mbeans_visibility_in_oracle
Oracle WebLogic Server (WLS) 12.2.1では、 Multi-Tenancy (WLS MT)と呼ばれる機能をサポートしています。WLS MTではパーティション、パーティション管理者、パーティションリソースというコンセプトが導入されました。ドメイン中のリソース、例えばMBeanにアクセスする際にパーティション分離を強制します。WLS管理者はドメインやパーティションのMBeanを見ることができますが、パーティション管理者だけでなく他のパーティションロールは自身のパーティションにあるMBeanしか見ることはできません。
このエントリでは、アプリケーションMBeanの可視性サポートを説明して、WLS MT 12.2.1のパーティション分離を紹介します。この説明には以下の内容をふくみます
- WLS MTでのアプリケーションMBeanの可視性に関する概要
- どのMBeanがWLS MBeanServerに登録され、どのMBeanがWLS管理者もしくはパーティション管理者から見えるのかを説明するシンプルなユーザーケース
- 詳細情報の参考記事へのリンク
このエントリで取り上げるユースケースは以下のエントリで作成したドメインを基にしています。
Create WebLogic Server Domain with Partitions using WLST in 12.2.1
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/create_weblogic_server_domain_with
http://orablogs-jp.blogspot.jp/2015/11/create-weblogic-server-domain-with.html
このエントリでは、以下の内容を説明しています。
- ドメイントポロジの概要紹介
- ドメインやパーティションへのアプリケーションデプロイ方法の説明
- JMXクライアントからグローバル/ドメインURLやパーティション固有のURLで、アプリケーションMBeanにアクセスする方法の説明
- デバッグ、ロギングの有効化方法の説明
1. Overview
アプリケーションをパーティション毎にWebLogic Serverにデプロイできるので、アプリケーションを複数のパーティションに対して複数配置します。WebLogic Serverには以下のMBeanServerがあります。
- Domain Runtime MBeanServer
- Runtime MBeanServer
各MBeanServerをすべてのパーティション用に使うことができます。WebLogic Serverはアプリケーションが各MBeanServerに登録したMBeanが各パーティションで一意であることを保証する必要があります。
WLS MTでのアプリケーションMBeanの可視性をいくつかのパートで説明します。
- Partition Isolation
- Application MBeans Registration
- Query Application MBeans
- Access Application MBeans
1.1 Partition Isolation
WLS管理者はパーティションMBeanを見ることができますが、パーティション管理者はドメインや他のパーティションのMBeanを見ることはできません。
1.2 Application MBeans Registration
アプリケーションをパーティションにデプロイする間にアプリケーションMBeanを登録します。WebLogic ServerはアプリケーションMBeanをWLS MBeanServerに登録する際に、パーティション固有のキー(例:Partition=<パーティション名>)をMBean Object Namesに追加します。こうして、増加したアプリケーションから登録された場合に、MBeanオブジェクト名が一意になることを保証します。
右図では、ドメインやパーティションのWLS MBeanServerに登録した際にアプリケーションMBean Object Nameが異なるさまを示しています。
![]()
右図ではWebLogicドメインとアプリケーションがあることを示しています。
WebLogicドメインは2個のパーティション(cokeとpepsi)で構成されています。
アプリケーションデプロイ中にアプリケーションがMBeanを登録します(例:testDomain:type=testType)。
アプリケーションをWebLogicドメイン、cokeパーティション、pepsiパーティションにデプロイします。WLS MBeanServerインスタンスはドメイン、cokeパーティション、pepsiパーティションが共有しています。
3回のアプリケーションデプロイメントの結果、3個のアプリケーションMBeanが同じMBeanServerに登録されています。
- ドメイン所属のMBean: testDomain:type=testType
- cokeパーティション所属のMBean: testDomain:Partition=cokePartition,type=testType
- pepsiパーティション所属のMBean: testDomain:Partition=pepsiPartition,type=testType
パーティションに属するMBeanには、ObjectNameのPartitionキープロパティが含まれています。
1.3 Query Application MBeans
WebLogic WLSTやJConsoleといったJMXクライアントでグローバル/ドメインURLやパーティション固有のURLに接続し、WebLogic MBeanServerに対しクエリを実行すると、異なるクエリ結果が返ってきます。
- グローバル/ドメインURLに接続する場合、パーティション所属のアプリケーションMBeanは接続したJMXクライアントから見える。
- パーティション固有のURLに接続する場合、WebLogic Serverがクエリ結果にフィルタを掛け、パーティション所属のアプリケーションMBeanのみ返す。ドメインや他パーティション所属のMBeanは見えない。
1.4 Access Application MBeans
WebLogic WLSTやJConsoleといったJMXクライアントがパーティション固有のURLに接続し、 getAttribute(<MBean ObjectName>, <attributeName>)のようなJMXの操作を実行すると、実のところ異なるMBeanに対してJMX操作を実行します。
- グローバル/ドメインURLに接続する場合、ドメイン所属のMBean(MBean ObjectNameでPartitionキープロパティのないMBean)のgetAttribute()を呼び出す
- パーティション固有のURLに接続する場合、パーティション所属のMBean(MBean ObjectNameでPartitionキープロパティがあるMBean)のgetAttribute()を呼び出す
2. Use case
それでは、MBeanの可視性がWebLogic Server 12.2.1のMultitenancyでパーティション分離をサポートするためにどのように作用するのか説明します。
2.1 Domain with Partitions
以下のエントリで、2個のパーティション(cokeとpepsi)を持つドメインを作成しています。
Create WebLogic Server Domain with Partitions using WLST in 12.2.1
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/create_weblogic_server_domain_with
http://orablogs-jp.blogspot.jp/2015/11/create-weblogic-server-domain-with.html
このドメインを再度このエントリのユースケースのために利用します。以下はドメイントポロジのサマリです。
- ドメインは1個の管理サーバ(admin)、cokeとpepsiというパーティションで構成されている。
- cokeパーティションには1個のリソースグループ (coke-rg1) を含み、仮想ターゲット(coke-vt)に向けられている
- pepsiパーティションには1個のリソースグループ (pepsi-rg1) を含み、仮想ターゲット(pepsi-vt)に向けられている
より具体的に、各ドメイン/パーティションには以下の値で構成されています。
| Domain Name | User Name | Password |
|---|
| Domain | base_domain | weblogic | welcome1 |
| Coke Partition | coke | mtadmin1 | welcome1 |
| Pepsi Partition | pepsi | mtadmin2 | welcome2 |
このドメイン作成方法の詳細は上記リンクをご覧ください。
2.2 Application deployment
ドメインをセットアップして開始し、アプリケーション"helloTenant.ear"をドメインにデプロイします。パーティションcokeのリソースグループcoke-rg1とパーティションpepsiのリソースグループpepsi-rg1にもデプロイします。デプロイはWLST、Fusion Middleware ControlといったWebLogic Serverのツールで可能です。以下はドメインとパーティションにアプリケーションをデプロイするためのWLSTコマンドの例です。
startEdit()
deploy(appName='helloTenant',target='admin,path='${path-to-the-ear-file}/helloTenant.ear')
deploy(appName='helloTenant-coke',partition='coke',resourceGroup='coke-rg1',path='${path-to-the-ear-file}/helloTenant.ear')
deploy(appName='helloTenant-pepsi',partition='pepsi',resourceGroup='pepsi-rg1',path='${path-to-the-ear-file}/helloTenant.ear')
save()
activate()
別のWLSデプロイメントツールについては、Referenceセクションをご覧ください。
2.3 Access Application MBeans
アプリケーションデプロイメントの間に、アプリケーションMBeanがWebLogic Server MBeanServerに登録されます。[1.2 Application MBean Registration]でお伝えした通り、1個のアプリケーションしかないにもかかわらず、複数のMBeanが登録されています。
アプリケーションMBeansにアクセスするには複数の方法があります。
2.3.1 WLST
WebLogic Scripting Tool (WLST) はコマンドラインスクリプティングインターフェースで、システム管理者やオペレータがWebLogic Serverインスタンスやドメインを監視・管理するために使います。WLSTを開始するには以下のコマンドを実行します。
$MW_HOME/oracle_common/common/bin/wlst.sh
WLSTが起動すると、ユーザーは接続URLを指定してサーバに接続することができます。以下は異なるアプリケーションMBean属性の値を示しています。WebLogic Server管理者やパーティション管理者が異なる接続URLを使った際には異なるアプリケーションMBean属性値が表示されます。
2.3.1.1 WLS administrator
WebLogic Server管理者 'weblogic'は以下の接続コマンドを使ってドメインに接続します。
connect("weblogic", "welcome1", "t3://localhost:7001")
下図はWebLogic Server MBeanServerに登録された3個のMBeanを示しています。なお、ドメイン名はtest.domain、各MBeanのPartitionName属性値は以下の通りです。
- test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName
- パーティションcokeに属している。PartitionName属性値はcoke
- test.domain:Partition=pepsi,type=testType,name=testName
- パーティションpepsiに属している。PartitionName属性値はpepsi
- test.domain:type=testType,name=testName
- ドメインに属している。ObjectNameのPartitionキープロパティはない。PartitionName属性はDOMAIN
パーティション所属のMBeanにはObjectName中にPartitionキープロパティがあります。パーティションコンテキストに登録する際にWebLogic Serverが内部でPartitionキープロパティを追加します。
![]()
2.3.1.2 Partition administrator for coke
同様に、パーティションcokeの管理者mtadmin1はパーティションcokeに接続できます。接続URLは仮想ターゲットcoke-vt(<Domain_Home>/config/config.xmlをチェックしてください)で定義されたURI接頭辞である/cokeを使います。
connect("mtadmin1", "welcome1", "t3://localhost:7001/coke")
下図のように、パーティションcokeに接続すると、1個だけMBeanが表示されます。
test.domain:type=testType,name=testName
PartitionキープロパティがObjectNameにありませんが、このMBeanはパーティションcokeに属しています。PartitionName属性値はcokeです。
![]()
2.3.1.3 Partition administrator for pepsi
同様に、パーティションpepsiの管理者mtadmin2はパーティションpepsiに接続できます。接続URLは仮想ターゲットpepsi-vt(<Domain_Home>/config/config.xmlをチェックしてください)で定義されたURI接頭辞である/pepsi を使います。
connect("mtadmin2", "welcome2", "t3://localhost:7001/pepsi")
下図のように、パーティションpepsiに接続すると、1個だけMBeanが表示されます。
test.domain:type=testType,name=testName
PartitionキープロパティがObjectNameにありませんが、パーティションcokeの管理者の場合と同様、このMBeanはパーティションpepsiに属しています。PartitionName属性値はpepsiです。
![]()
2.3.2 JConsole
JConsoleはJDKに組み込まれたGUIのツールで、Java Management Extensions (JMX)仕様に準拠した監視ツールです。JConsoleを使うと、MBeanServerに登録されたMBeanの概要をつかむことができます。
JConsoleを起動するには以下のコマンドを実行します。
$JAVA_HOME/bin/jconsole
-J-Djava.class.path=$JAVA_HOME/lib/jconsole.jar:
$JAVA_HOME/lib/tools.jar:$MW_HOME/wlserver/server/lib/wljmxclient.jar
-J-Djmx.remote.protocol.provider.pkgs=weblogic.management.remote
ここで<MW_HOME>はWebLogic Serverをインストールした場所です。
JConsoleが起動したら、WebLogic Server管理者やパーティション管理者は資格証明とJMXサービスURLを指定した後に、MBeanを確認することができます。
2.3.2.1 WLS administrator
WebLogic Server管理者weblogicはJMXサービスURLを指定して、WebLogic Server Runtime MBeamServerに以下のように接続します。
service:jmx:t3://localhost:7001/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime
WebLogic Server管理者が接続すると、JConsoleのMBeanツリーにはObjectNameにtest.domainを持つ3個のMBeanが表示されています。
下図の右ペインで示したObjectNameはパーティションcokeに属しており、Partitionキープロパティを有しています(Partition=coke)。
![]()
下図の場合パーティションpepsiに属するMBeanなので、Partitionキープロパティを有しています(Partition=pepsi)。
![]()
下図の場合、ドメインに属するMBeanなので、Partitionキープロパティはありません。
![]()
WebLogic Server管理者がWLSTで見たものとここで表示した結果は同じですね。
2.3.2.2 Partition administrator for coke
パーティション管理者mtadmin1は異なるJMXサービスURLをJConsoleに指定します。
service:jmx:t3://localhost:7001/coke/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime
パーティション固有のJMXサービスURLを使って接続すると、パーティション管理者には1個のMBeanしか見えません。
test.domain:type=testType,name=testName
このMBeanはパーティションcokeに属しており、下図の通り、PartitionName属性値はcokeです。しかし、ObjectNameにPartitionキープロパティはありません。
![]()
![]()
2.3.2.3 Partition administrator for pepsi
パーティション管理者mtadmin2は異なるJMXサービスURLをJConsoleに指定します。
service:jmx:t3://localhost:7001/pepsi/pepsi/weblogic.management.mbeanservers.runtime
パーティション固有のJMXサービスURLを使って接続すると、パーティション管理者mtadmin2には1個のMBeanしか見えません。
test.domain:type=testType,name=testName
このMBeanはパーティションpepsiに属しており、下図の通り、PartitionName属性値はpepsiです。
![]()
![]()
2.3.3 JSR 160 APIs
JMXクライアントはJSR 160 APIを使ってMBeanServerに登録されたMBeanにアクセスすることができます。例えば以下のコードでは、サービスURLと環境をMBean属性に指定してJMXConnetorを取得しています。
import javax.management.*;
import javax.management.remote.JMXConnector;
import javax.management.remote.JMXServiceURL;
import javax.management.remote.JMXConnectorFactory;
import java.util.*
public class TestJMXConnection {
public static void main(String[] args) throws Exception {
JMXConnector jmxCon = null;
try {
// Connect to JMXConnector
JMXServiceURL serviceUrl = new JMXServiceURL(
"service:jmx:t3://localhost:7001/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime");
Hashtable env = new Hashtable();
env.put(JMXConnectorFactory.PROTOCOL_PROVIDER_PACKAGES, "weblogic.management.remote");
env.put(javax.naming.Context.SECURITY_PRINCIPAL, "weblogic");
env.put(javax.naming.Context.SECURITY_CREDENTIALS, "welcome1");
jmxCon = JMXConnectorFactory.newJMXConnector(serviceUrl, env);
jmxCon.connect();
// Access the MBean
MBeanServerConnection con = jmxCon.getMBeanServerConnection();
ObjectName oname = new ObjectName("test.domain:type=testType,name=testName,*");
Set<objectname> queryResults = (Set<objectname>)con.queryNames(oname, null);
for (ObjectName theName : queryResults) {
System.out.print("queryNames(): " + theName);
String partitionName = (String)con.getAttribute(theName, "PartitionName");
System.out.println(", Attribute PartitionName: " + partitionName);
}
} finally {
if (jmxCon != null)
jmxCon.close();
このコードをコンパイルして実行するためには、wljmxclient.jarをクラスパスに指定する必要があります。
$JAVA_HOME/bin/java -classpath $MW_HOME/wlserver/server/lib/wljmxclient.jar:. TestJMXConnection
以下のような結果が出力されるはずです。
Connecting to: service:jmx:t3://localhost:7001/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime
queryNames(): test.domain:Partition=pepsi,type=testType,name=testName, Attribute PartitionName: pepsi
queryNames(): test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName, Attribute PartitionName: coke
queryNames(): test.domain:type=testType,name=testName, Attribute PartitionName: DOMAIN
パーティション管理者mtadmin1を使うようにコードを変更すると、以下のようになります。
JMXServiceURL serviceUrl = new JMXServiceURL(
"service:jmx:t3://localhost:7001/coke/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime");
env.put(javax.naming.Context.SECURITY_PRINCIPAL, "mtadmin1");
env.put(javax.naming.Context.SECURITY_CREDENTIALS, "welcome1");
コードを実行すると、1個のMBeanしか返ってこないことがわかります。
Connecting to: service:jmx:t3://localhost:7001/coke/jndi/weblogic.management.mbeanservers.runtime
queryNames(): test.domain:type=testType,name=testName, Attribute PartitionName: coke
同様の結果がパーティション管理者pepsiを使った場合に確認できるでしょう。パーティションpepsi固有のJMXサービスURLを指定すると、パーティションpepsiに属するMBean1個のみが返ってきます。
2.4 Enable logging/debugging flags
WebLogic Server 12.2.1でMBeanが正しい挙動を示さないことがあります。例えば、
- MBeanのクエリを発行した際に、パーティション管理者がグローバルドメインや別のパーティションのMBeanを見ることができる。
- JMX例外が発生する。例えば、MBeanにアクセスする際に、javax.management.InstanceNotFoundExceptionが発生する。
エラーの切り分けのために以下のことを試行してください。
- JConsoleの接続問題の場合、JConsole起動時にコマンドラインに -debug を追加する
- MBeanのクエリを発行すると、パーティション管理者がグローバルドメインや別パーティションのMBeanを見ることができる場合、
- WLSTやJConsole、JSR 160 APIといったJMXクライアントから接続している場合、サービスのホスト名が<Domain_Home>/config/config.xmlの仮想ターゲットで定義したホスト名に一致することを確認する。
- サービスURLのURI接頭辞が<Domain_Home>/config/config.xmlの仮想ターゲットで定義したURI接頭辞と一致することを確認する。
- JMX例外が発生した場合、例えば、MBeanにアクセスする際に、javax.management.InstanceNotFoundExceptionが発生した場合
- MBeanがパーティションに属する場合、パーティションを開始します。アプリケーションデプロイメントはパーティションが開始しないと実行されません。
- 以下のオプションを追加して、サーバー始動時にデバッグフラグを有効にします。
-Dweblogic.StdoutDebugEnabled=true -Dweblogic.log.LogSeverity=Debug -Dweblogic.log.LoggerSeverity=Debug -Dweblogic.debug.DebugPartitionJMX=true -Dweblogic.debug.DebugCIC=false
- 対象としている特定のMBean ObjectNameをサーバーログで探します。デバッグしているMBeanが正しくパーティション・コンテキストに登録されていることを確認します。MBeanオペレーションが正しくパーティションコンテキストで呼ばれていることを確認します。
以下はMBean"test.domain:type=testType,name=testName"のMBean登録、queryNames()、getAttribute()の呼び出しに関連するデバッグメッセージの例です。 <Oct 21, 2015 11:36:43 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <Calling register MBean test.domain:type=testType,name=testName in partition DOMAIN>
<Oct 21, 2015 11:36:44 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <Calling register MBean test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName in partition coke>
<Oct 21, 2015 11:36:45 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <Calling register MBean test.domain:Partition=pepsi,type=testType,name=testName in partition pepsi>
<Oct 21, 2015 11:36:56 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <queryNames on MBean test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName,* in partition coke>
<Oct 21, 2015 11:36:56 PM PDT> <Debug> <MBeanCIC> <BEA-000000> <getAttribute: MBean: test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName, CIC: (pId = 2d044835-3ca9-4928-915f-6bd1d158f490, pName = coke, appId = helloTenant$coke, appName = helloTenant, appVersion = null, mId = null, compName = null)>
- パーティションコンテキストが正しくない理由を確認するため、上記のデバッグフラグに加え、以下のデバッグフラグを追加して、WebLogic Serverを始動してください。
-Dweblogic.debug.DebugCIC=true. Once this flag is used, there are a lot of messages logged into the server log. Search for the messages logged by DebugCIC logger, like ExecuteThread: '<thread id #>' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'): Pushed
以下はDebugPartitionJMX ロガーがログ出力したメッセージの例です。
<Oct 21, 2015, 23:59:34 PDT> INVCTXT (24-[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'): Pushed [(pId = 0, pName = DOMAIN, appId = null, appName = null, appVersion = null, mId = null, compName = null)] on top of [(pId = 0, pName = DOMAIN, appId = null, appName = null, appVersion = null, mId = null, compName = null)]. New size is [2]. Pushed by [weblogic.application.ComponentInvocationContextManagerImpl.pushComponentInvocationContext(ComponentInvocationContextManagerImpl.java:173)
...
<Oct 21, 2015 11:59:34 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <Calling register MBean test.domain:type=testType,name=testName in partition DOMAIN>
...
<Oct 21, 2015, 23:59:37 PDT> INVCTXT (29-[STANDBY] ExecuteThread: '2' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'): Pushed [(pId = 2d044835-3ca9-4928-915f-6bd1d158f490, pName = coke, appId = helloTenant$coke, appName = helloTenant, appVersion = null, mId = null, compName = null)] on top of [(pId = 2d044835-3ca9-4928-915f-6bd1d158f490, pName = coke, appId = null, appName = null, appVersion = null, mId = null, compName = null)]. New size is [3]. Pushed by
[weblogic.application.ComponentInvocationContextManagerImpl.pushComponentInvocationContext(ComponentInvocationContextManagerImpl.java:173)
...
<Oct 21, 2015 11:59:37 PM PDT> <Debug> <PartitionJMX> <BEA-000000> <Calling register MBean test.domain:Partition=coke,type=testType,name=testName in partition coke>
3. Conclusion
WebLogic Server 12.2.1はMulti-Tenancy (MT)という新機能を提供しています。この機能を使って、パーティション分離が強制されています。アプリケーションをドメインやパーティションにデプロイできます。パーティションのユーザーは別のパーティションに所属するリソース(アプリケーションが登録したMBeanを含む)を見ることができません。このエントリでは、あるユースケースを使い、アプリケーションMBeanがパーティション分離が、MBeanの可視性でどのように影響するのかを御所階しました。詳細情報は、Referencesセクションをご覧ください。
4. References
Oracle® Fusion Middleware Installing and Configuring Oracle WebLogic Server and Coherence 12c (12.2.1)
Creating and Configuring the WebLogic Domain
https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/WLSIG/GUID-4AECC00D-782D-4E77-85DF-F74DD61391B4.htm#WLSIG281
Oracle® Fusion Middleware Installing and Configuring the Oracle Fusion Middleware Infrastructure 12c (12.2.1)
Configuring the Oracle Fusion Middleware Infrastructure Domain
https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/INFIN/GUID-CA80A6E9-8903-4E19-81D7-A3647A11D0A6.htm#INFIN280
Oracle® Fusion Middleware WLST Command Reference for WebLogic Server 12c (12.2.1)
https://docs.oracle.com/middleware/1221/wls/WLSTC/toc.htm
Java SE Monitoring and Management Guide
Using JConsole
http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/management/jconsole.html
Managing WebLogic Server with JConsole
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/managing_weblogic_servers_with
JSR 160: Java Management Extensions Remote JMX api
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=160
Oracle® Fusion Middleware Administering Security for Oracle WebLogic Server 12.2.1 12c (12.2.1)
Configuring Security for a WebLogic Domain
http://docs.oracle.com/middleware/1221/wls/SECMG/conf-security-for-domain.htm#SECMG777
Oracle® Fusion Middleware Deploying Applications to Oracle WebLogic Server 12c (12.2.1)
Understanding WebLogic Server Deployment
https://docs.oracle.com/middleware/1221/wls/DEPGD/understanding.htm#DEPGD114

















 各パーティションのターゲットとして、パーティションのアプリケーションやリソースを実行させたい管理対象サーバーのクラスタを指定できます (ターゲットの詳細については後述します)。同一クラスタに複数のパーティションをターゲットにしている場合でも、独立して各パーティションを起動したりシャットダウンしたりすることができます。異なるパーティションに異なるセキュリティレルムを使わせることができます。
各パーティションのターゲットとして、パーティションのアプリケーションやリソースを実行させたい管理対象サーバーのクラスタを指定できます (ターゲットの詳細については後述します)。同一クラスタに複数のパーティションをターゲットにしている場合でも、独立して各パーティションを起動したりシャットダウンしたりすることができます。異なるパーティションに異なるセキュリティレルムを使わせることができます。 先述のように、2個の別のドメインを使おう(一つはHRアプリケーション、もう一つは財務アプリケーション)と考えている場合、2個のパーティションを含む1個のドメインを使うことができます。一つのパーティションにHRアプリケーション、もう一つに財務アプリケーションという具合です。簡単な例として、HRパーティションにはHRアプリケーションとリソースを含むリソースグループがあり、financeパーティションには財務アプリケーションとリソースを含むリソースグループがあるとしましょう。12.2.1では、実のところ各リソースグループをターゲットにします。理に適っていれば、HRパーティションとfinanceパーティションの両方のリソースグループを同一クラスタへ向けることもできます。そして、パーティションはそれぞれ独立して管理できるので、別のパーティションを邪魔せずに起動、停止することができます。クラスタの管理対象サーバはずっと起動したままです。パーティションの立ち上げ、立ち下げ時に、パーティションのリソースグループ中のアプリケーションやリソースが立ち上がったり立ち下がったりするのであって、サーバ全体の立ち上げ・立ち下げではありません。
先述のように、2個の別のドメインを使おう(一つはHRアプリケーション、もう一つは財務アプリケーション)と考えている場合、2個のパーティションを含む1個のドメインを使うことができます。一つのパーティションにHRアプリケーション、もう一つに財務アプリケーションという具合です。簡単な例として、HRパーティションにはHRアプリケーションとリソースを含むリソースグループがあり、financeパーティションには財務アプリケーションとリソースを含むリソースグループがあるとしましょう。12.2.1では、実のところ各リソースグループをターゲットにします。理に適っていれば、HRパーティションとfinanceパーティションの両方のリソースグループを同一クラスタへ向けることもできます。そして、パーティションはそれぞれ独立して管理できるので、別のパーティションを邪魔せずに起動、停止することができます。クラスタの管理対象サーバはずっと起動したままです。パーティションの立ち上げ、立ち下げ時に、パーティションのリソースグループ中のアプリケーションやリソースが立ち上がったり立ち下がったりするのであって、サーバ全体の立ち上げ・立ち下げではありません。 しかしこの場合、リソース・グループは、それ自体でアプリケーションやリソースを定義しておらず、代わりにHRリソースグループテンプレートを参照しています。そして、ある顧客が両アプリケーションを使いたい場合には、当該顧客のパーティションに2個目のリソースグループを作成し、もう一方のリソースグループテンプレートに作成したリソースグループを紐付けます。顧客の1社に対応するパーティションを起動すると、WebLogic Serverは基本的にリソースグループテンプレートに定義されているように、当該顧客用のアプリケーションやリソースのコピーを起動します。そして、もう一方の顧客のパーティションを起動すると、WebLogic Serverはそのアプリケーションやリソースの顧客用のコピーを始動します。
しかしこの場合、リソース・グループは、それ自体でアプリケーションやリソースを定義しておらず、代わりにHRリソースグループテンプレートを参照しています。そして、ある顧客が両アプリケーションを使いたい場合には、当該顧客のパーティションに2個目のリソースグループを作成し、もう一方のリソースグループテンプレートに作成したリソースグループを紐付けます。顧客の1社に対応するパーティションを起動すると、WebLogic Serverは基本的にリソースグループテンプレートに定義されているように、当該顧客用のアプリケーションやリソースのコピーを起動します。そして、もう一方の顧客のパーティションを起動すると、WebLogic Serverはそのアプリケーションやリソースの顧客用のコピーを始動します。