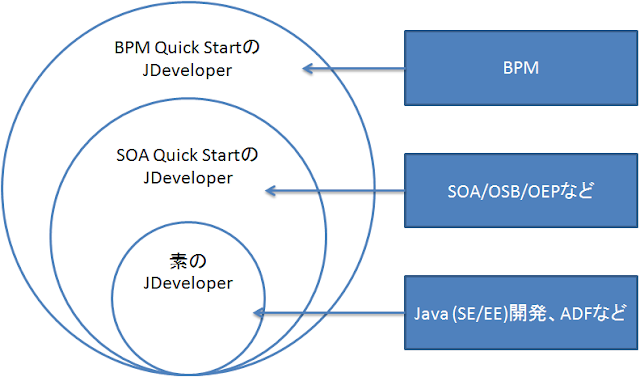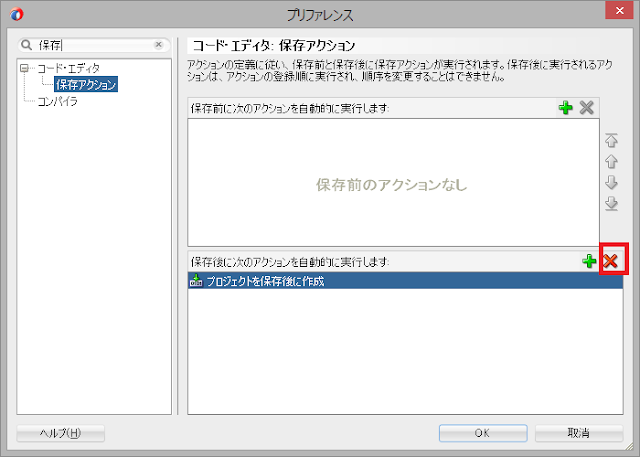原文はこちら。
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/wls_mt_diagnostics_overview
WebLogic Serverへのパッチ適用やアップデートがずっと簡単になりました。Zero Downtime Patchingのリリースは、WebLogic Serverのメンテナンスの簡素化と、継続的な可用性を提供する機能に対するOracleのコミットメントにおいて、大きな前進を示すものです。
Zero Downtime Patchingを使うと、配布されたパッチを複数のクラスタやドメイン全体に対し、1コマンドでロールアウトできます。このとき、エンドユーザー向けのサービス停止やセッションデータの損失を引き起こすことはありません。かつては退屈で時間のかかるタスクだったものが、一貫性のある、効率的で柔軟な自動化されたプロセスに置き換わります。
このプロセスを自動化することにより、人手による入力(つまりエラーを引き起こす要因)を劇的に削減することができ、変更前に、入力内容を検証することができます。これはプロセスの一貫性および信頼性に大きな影響があり、またプロセスの効率を劇的に向上するものです。
エラーが発生したときにステップを再試行できたり、問題解決のため一時停止、中断した箇所から再開できたり、もしくは必要であれば、環境全体を元の状態に戻すことができたりする、という点で、プロセスには弾力性があります。
管理者は、パッチを適用したOracleHomeアーカイブを既存の慣れたツールで作成・確認検証し、アーカイブをアップグレードしたい各ノードに配置してから、以下のシンプルなコマンドで以後の処理を実行します。
サーバで利用しているJavaのアップデートや実行中のアプリケーションへのアップデートなどにも、同じプロセスを活用することができます。エンドユーザ向けのサービス停止はまったくありません。
ここで説明することになるであろうZero Downtime (ZDT) Patchingには、たくさんのおもしろい特徴がありますので、乞うご期待!
Zero Downtime Patchingに関する詳細は、以下のドキュメントをご覧ください。
https://blogs.oracle.com/WebLogicServer/entry/wls_mt_diagnostics_overview
WebLogic Serverへのパッチ適用やアップデートがずっと簡単になりました。Zero Downtime Patchingのリリースは、WebLogic Serverのメンテナンスの簡素化と、継続的な可用性を提供する機能に対するOracleのコミットメントにおいて、大きな前進を示すものです。
Zero Downtime Patchingを使うと、配布されたパッチを複数のクラスタやドメイン全体に対し、1コマンドでロールアウトできます。このとき、エンドユーザー向けのサービス停止やセッションデータの損失を引き起こすことはありません。かつては退屈で時間のかかるタスクだったものが、一貫性のある、効率的で柔軟な自動化されたプロセスに置き換わります。
このプロセスを自動化することにより、人手による入力(つまりエラーを引き起こす要因)を劇的に削減することができ、変更前に、入力内容を検証することができます。これはプロセスの一貫性および信頼性に大きな影響があり、またプロセスの効率を劇的に向上するものです。
エラーが発生したときにステップを再試行できたり、問題解決のため一時停止、中断した箇所から再開できたり、もしくは必要であれば、環境全体を元の状態に戻すことができたりする、という点で、プロセスには弾力性があります。
管理者は、パッチを適用したOracleHomeアーカイブを既存の慣れたツールで作成・確認検証し、アーカイブをアップグレードしたい各ノードに配置してから、以下のシンプルなコマンドで以後の処理を実行します。
rolloutOracleHome("Cluster1, Cluster2", "/pathTo/patchedOracleHome.jar", "/pathTo/backupOfUnpatchedOracleHome")サーバで利用しているJavaのアップデートや実行中のアプリケーションへのアップデートなどにも、同じプロセスを活用することができます。エンドユーザ向けのサービス停止はまったくありません。
ここで説明することになるであろうZero Downtime (ZDT) Patchingには、たくさんのおもしろい特徴がありますので、乞うご期待!
Zero Downtime Patchingに関する詳細は、以下のドキュメントをご覧ください。
Oracle® Fusion Middleware Administering Zero Downtime Patching Workflows 12c (12.2.1)
http://docs.oracle.com/middleware/1221/wls/WLZDT/index.html